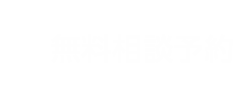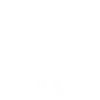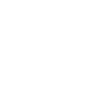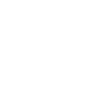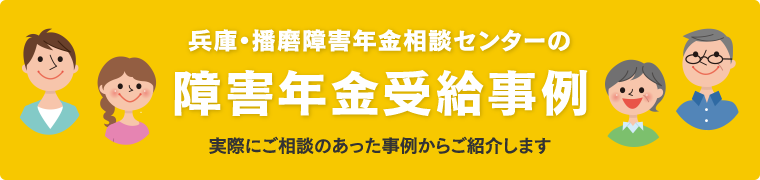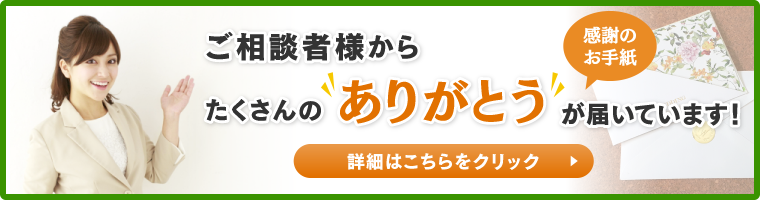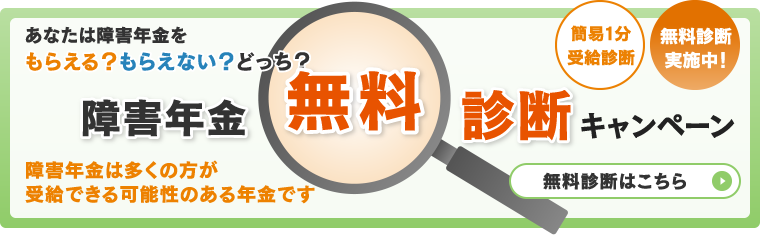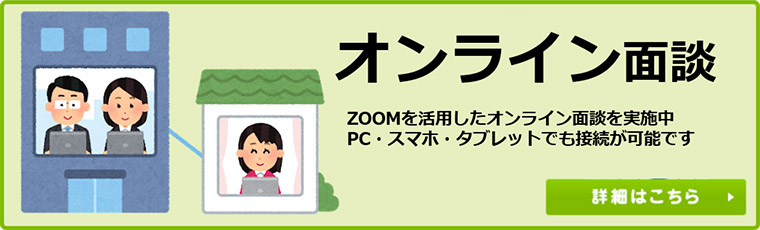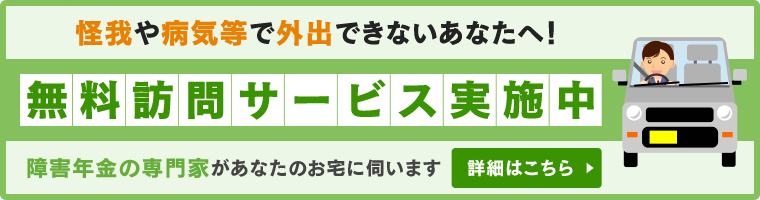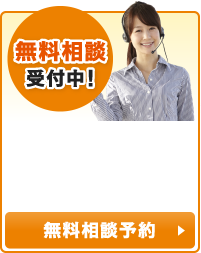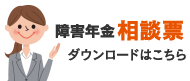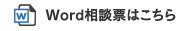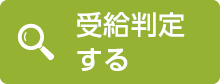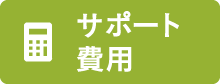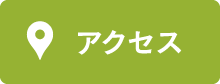診断名より“日常生活ができない”が大事!障害年金の本質に迫る
症状名だけでは通らない。審査官が本当に見るものは「あなたの暮らしの困難さ」です
症状を持っているだけで年金が認められるわけではありません。
うつ病、発達障害、高次脳機能障害──どれも「診断名」を耳にすれば重く響く傷病ですが、それだけでは障害年金は支給されないことが多いのです。
審査で本当に問われるのは、「〇〇ができない」というあなたの 日常生活の制限。
朝起きられない、書類をまとめられない、薬を飲み忘れて通院できない、対人場面でパニックになる――こうした“できないこと”を具体的に伝えることが、通るか否かの分かれ目になります。
本記事では、「診断名に頼らない実態評価」の視点から、審査で重視される日常生活能力の基準、注意すべき記載例、そしてあなたができる準備を丁寧に解説します。
目次
第1章:診断名だけでは年金は通らない理由
障害年金の審査では、診断名(たとえば「うつ病」「発達障害」「高次脳機能障害」)そのものが合格を保証するわけではありません。
なぜなら、制度が見るのは「その傷病によって日常生活にどれだけ制限が出ているか」、つまり 実際に“できないこと”がどれほどあるか だからです。
たとえ診断名が重くても、日常生活や就労に支障があるという具体的な記述がなければ、審査側には「生活に問題はない」と判断されてしまう可能性があります。
第2章:障害年金で重視される “日常生活能力” とは何か
精神障害(うつ・発達障害・高次脳機能障害など)での審査においては、診断書(精神の障害用) の記載要領に
「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」という2つの評価軸が含まれています。
日常生活能力の判定(7項目 × 4段階評価)
診断書では、次の7つの場面における制限度合いを、4段階で評価する「判定」欄があります。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持(入浴・洗面・衣服更衣など)
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会性
それぞれに「①できる」「②おおむねできるが助言・指導を要する」「③助言・指導があればできる」「④助言・指導してもできない」という段階があり、
これを数値(1~4)に置き換えて平均を出します。
この「判定平均」と、もう一つの軸である「日常生活能力の程度」評価を組み合わせて、等級の目安とされます
日常生活能力の程度(5段階評価)
こちらは、日常生活全体としてどの程度制限を受けているかを5段階で包括的に評価する欄です。
例えば、
- (1)症状はあるが生活に支障はほとんどない
- (5)身の回りのこともほとんどできず常時の援助が必要
といったレベルで区分されます。
この「程度」と「判定平均」の組み合わせが、等級を判断する目安になります。
ただし、これはあくまで「目安」であり、実際の等級判定は診断書全体の記載内容や他の資料との整合性を見て総合判断されるため注意が必要です。
第3章:具体例でわかる “できないこと” の伝え方(傷病別シナリオ)
以下のような例を参考にして、自分の生活で“できないこと”を具体的にまとめて医師に伝えると、診断書の内容が変わる可能性があります。
傷病名 | 『できないこと』の例 | 書き方・伝え方のコツ |
うつ病 | 朝起きられない、身支度が整わない、外出できない、家事ができない | 「起床後すぐベッドから動けない」「朝食準備に30分かかる」「週1~2回しか買い物できない」など、時間・頻度・具体的行動を記録して伝える |
発達障害(ASD/ADHD) | 書類整理ができない、忘れやすい、手順を追えない、対人応対が困難 | 「請求書類をまとめるのに数時間かかる」「銀行窓口で緊張して話せない」「連絡メールを見落としがち」など、実際の失敗例を伝える |
高次脳機能障害 | 記憶保持できない、段取りができない、注意が続かない | 「10分前にやることを忘れる」「薬を複数回飲み忘れる」「途中で別のことを始めて元に戻れない」などを具体例で |
このように具体的に医師に伝え、診断書に「生活能力の判定」欄に反映されていれば、審査側には「日常生活に支障がある実態」が伝わりやすくなります。
ご本人様が伝えるのが困難なようでしたら同席したご家族やメモなどを利用し、日常生活の現状を伝えるとよいでしょう。(第5章を参考にしてみてください)
第4章:よくある記載ミスとリスク
📌「できる」表現が多すぎる
日常生活欄に「できる」「自立可能」とだけ書かれると、審査側には「問題ない」と判断されてしまう危険があります。
📌支援・援助前提で「できる」と書かれている
しかし記載要領では、援助なしで生活した場合を想定して書くべきとされており、過度に支援環境を前提に書くと過大評価のリスクがあります。
📌現症のみで判断してしまう
症状が変動する精神疾患では、良い日だけで書かれると軽く見られがち。過去1年程度の変動を含めて「増悪と軽快の波」を伝えるべきです。
📌矛盾する記載がある
病名・病歴・日常生活能力の記述がつじつまが合わなかったり、過去の状態と現在の能力の記述に食い違いがあると、審査官から疑義を持たれる可能性があります。
第5章:あなたができる準備と行動ステップ
📌日常の記録をつける
1週間~1ヵ月程度、朝起きる時間から就寝まで「できなかったこと」や「無理だった動作」をメモ
通院・服薬・休息などの時間も記録
📌家族・支援者の視点を取る
家族や支援者から見た「日常で困っている場面」を聞き、メモしておく
支援者証言を補助資料として提出可能な場合も
📌診察時に伝えるポイントを整理する
「今日は調子がいい」日を見せるのではなく、日常生活の平均的な状態を伝える
記録を持参し、「このような日に何ができなかったか」を具体的に見せる
📌診断書下書きを医師と擦り合わせる
医師に診断書案を見せて、誤記や記載漏れをチェック
支援・助言前提かどうか、変動性や援助の必要性も含めて補足説明書(意見書)を付けてもらう
📌補助資料を揃える
通院履歴、薬歴、診療報酬明細、検査結果、手帳・福祉サービス利用記録 など
申立書(病歴・就労状況等申立書)で“できないことの実情”を別記
📌専門家に相談する
社会保険労務士など、障害年金に詳しい専門家に書類チェックやアドバイスをもらう
まとめ:審査官にあなたの現実を理解してもらいましょう
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
「診断名」を持つあなたは、その病気が人生に影響を及ぼしている証拠を持っています。
ただ、それを制度につなげるためには、“できないこと”を正確に伝える言葉 が必要です。
診断書や申立書に、あなたの苦しみや日常の苦労を具体的に落とし込むことが、制度の審査官に“あなたの現実”を理解してもらう鍵となります。
躊躇せず、記録を取り、医師と率直に向き合い、支援を受けながら最善を尽くしてください。
もし書類のチェックや表現に不安があれば、ぜひ社会保険労務士などの専門家を頼ってください。
そして、あなたの「生活できない」事実を、制度に正しく評価してもらいましょう。
どうか一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性があるか、どうすれば可能性を最大限に高められるかを一緒に考えます。
初回のご相談は無料です。
あなたの心が少しでも軽くなり、安心して治療に専念できる未来のため、私たちが全力でサポートすることをお約束します。
↓今すぐ無料相談を予約する↓
お電話でのお問い合わせも歓迎しております。
TEL: 079-289-5623 (受付時間:平日9:00〜18:00)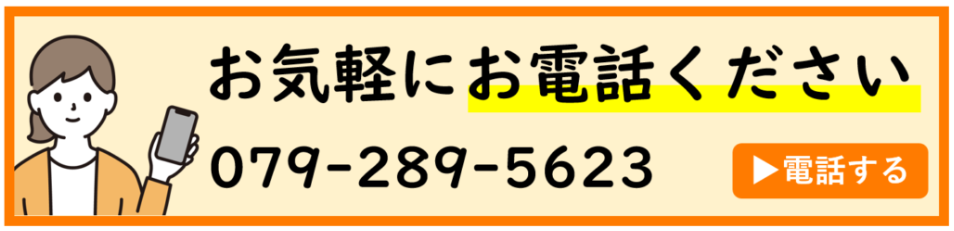
プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
お知らせの関連記事
- 兵庫県立播磨特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2026/01/16】
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 主治医に「診断書を書いてもらえない」「申請を拒まれた」と感じている方へ
- 兵庫県立出石特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2025/11/07】
- 姫路しらさぎ特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2025/11/04】
- 【2025年最新】双極性障害で障害年金はもらえる?社労士が等級認定・金額・申請方法を徹底解説
- 【2025年最新】うつ病の障害年金はいくらもらえる?社労士が申請条件から書類の書き方、コツまで徹底解説
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 夏季休業のご案内 2025年(令和7年)夏
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 障害年金の「障害認定日」とは?誤解されやすいポイントを詳しく解説
- 兵庫県立播磨特別支援学校に通学されているお子様の保護者の皆様に向けてセミナーを開催いたしました
- 冬季休業のご案内 令和6年 年末年始
- 就労移行支援事業所ウェルビー姫路駅前センター様で障害年金学習会を開催しました!
- 明石市在住の方へ7月21日(日)無料出張相談会開催します!!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 冬季休業のご案内 2023年冬
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2022年4月)
- 【LINE・メールは受付可】年末年始休業のお知らせ
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2021年4月)
- コロナうつと思われる方へ障害年金請求のご案内
- 事務所移転の御案内
- 相談者から頂いたアンケート32(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート31(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート30(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート29(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート27(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート26(加古川市)
- 相談者から頂いたアンケート25(朝来市)
- 相談者から頂いたアンケート24(揖保郡)
- 相談者から頂いたアンケート23(相生市)
- 相談者から頂いたアンケート22(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート21(加古川市)
- 相談者から頂いたアンケート20(鳥取県)
- 相談者から頂いたアンケート19(姫路市)
- 「年金生活者支援給付金」がはじまります。
- お盆期間の休業のお知らせ
- 相談者から頂いたアンケート18(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート17(高砂市)
- 相談者から頂いたアンケート16(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート14(加東市)
- 相談者から頂いたアンケート15(赤穂市)
- 相談者から頂いたアンケート13
- 相談者から頂いたアンケート12
- 相談者から頂いたアンケート11
- 相談者から頂いたアンケート10
- 相談者から頂いたアンケート9
- 相談者から頂いたアンケート8
- 相談者から頂いたアンケート7
- 相談者から頂いたアンケート6
- 相談者から頂いたアンケート5
- 相談者から頂いたアンケート4
- 相談者から頂いたアンケート3
- 相談者から頂いたアンケート2
- 相談者から頂いたアンケート1
障害年金についての関連記事
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金をもらうために知っておきたいこと
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 障害年金の不支給が増加!申請は社労士に依頼した方がいいのか
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 障害年金の「障害認定日」とは?誤解されやすいポイントを詳しく解説
- 障害年金の『初診日』の考え方とは??
- 【親なきあと】3つの課題と解決策|『親が元気なうちにできること』を考える
- うつ病で引きこもり・寝たきりの方へ:障害年金申請をご検討ください
- 統合失調症で障害年金を受け取るには?認定基準や申請のポイントを徹底解説!
- 障害者手帳と障害年金、違いと関係性を知っていますか?
- ADHDで障害年金を受給できる?認定基準や申請のポイントを徹底解説
- 糖尿病で障害年金を受給するには?
- 障害年金の遡及請求とは?受給のポイントと注意点を詳しく解説
- うつ病など精神疾患は障害年金の対象です!申請・請求のポイントを徹底解説!
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- うつ病で障害年金受給にデメリットはあるのか?4つの注意点と申請手順を社労士が解説!
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- 人工関節(人工股関節)で障害年金はいくら貰える?申請/受給のポイント・必要書類を社労士が徹底解説!
- 【社労士が解説】障害年金をご自分で申請したい方へ【依頼した方が良い場合・違いがでる点】
- 傷病手当金が切れたら申請するべき障害年金とは?切れる前に申請するべき理由は?
- 【まとめ】脳脊髄液減少症で障害年金を申請したい方へ