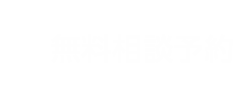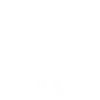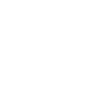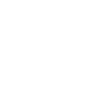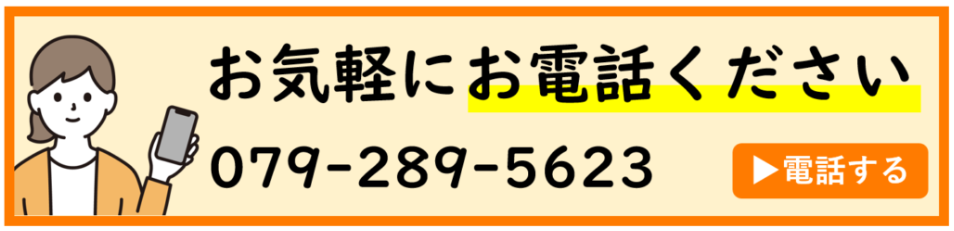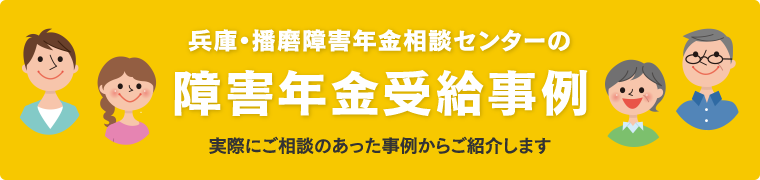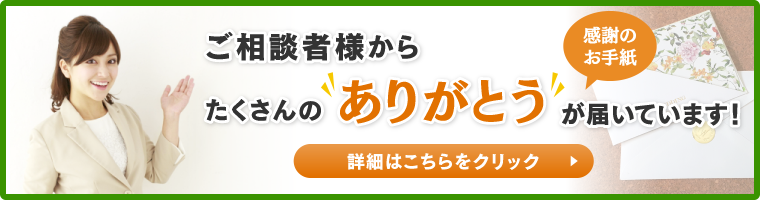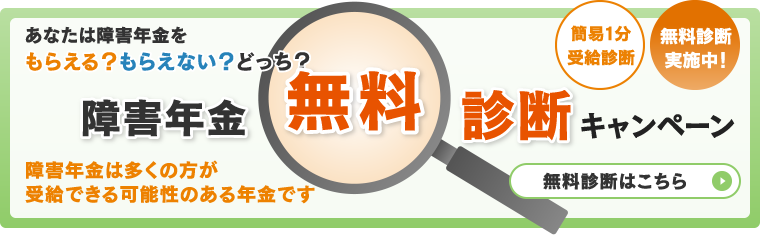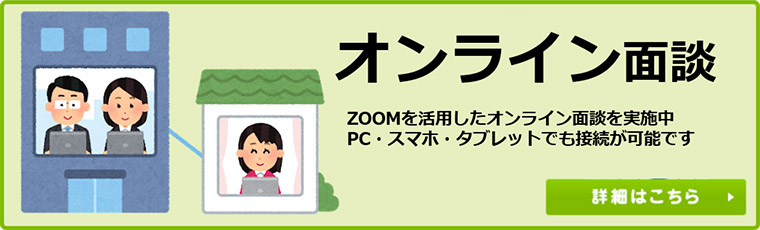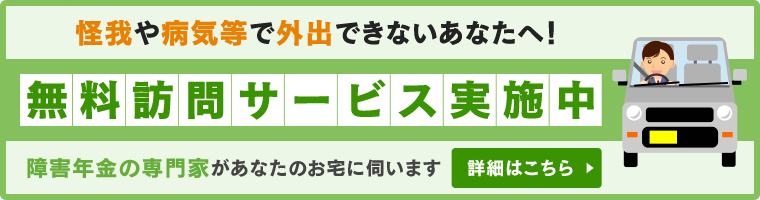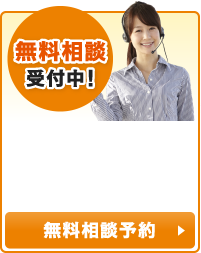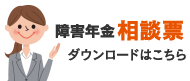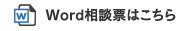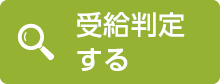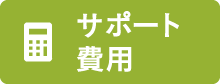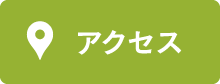障害年金の「障害認定日」とは?誤解されやすいポイントを詳しく解説
目次
障害認定日とは?障害年金申請のカギとなる日付
障害年金を申請する上で、「障害認定日」は非常に重要な日です。
これは、障害の程度を正式に判定する基準日であり、この日以降に障害の状態が一定基準に達していれば、年金を受給できる可能性が出てきます。
具体的には、以下のいずれかが障害認定日となります:
- 初診日から起算して1年6か月が経過した日(原則)
- 1年6か月より前に傷病が治った(症状が固定した)日(肢体障害などの特例の場合に限る、要相談ください)
ここで言う「治った」とは、治癒というより症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になったことを指します。
障害認定日と診断日・申請日の違いに注意!
よくある誤解の一つが、「医師から障害と診断された日が障害認定日」と思ってしまうことです。
しかし、診断された日がそのまま障害認定日になるわけではありません。
また、「申請日」=「障害認定日」と混同されることもありますが、これも誤りです。
📌障害認定日:障害状態を判断する基準日(制度的に決まった日)
📌診断日:1級~3級まであり、厚生年金加入中に初診日がある方が対象。
📌申請日:あなたが実際に障害年金を請求(提出)した日
これらの違いを正しく理解することが、スムーズな申請につながります。
障害認定日に該当しない場合でも諦めない!「事後重症」という制度
障害認定日時点では障害の程度が軽く、要件を満たさなかった場合でも、後に症状が重くなった時点で申請する方法があります。
これが「事後重症請求」です。
この方法では、現在の障害状態に基づいて審査され、
認定されれば請求(提出)した翌月から年金を受け取ることができます。
障害認定日を正確に把握するための書類とは?
障害認定日における障害の状態を証明するには、障害認定日当時の診断書が必要です。
ただし、当時の診断書が取得できない場合は以下のような方法も検討されます:
- 当時の紹介状のコピー
- 複数の医療機関の記録を組み合わせる
- 医師への事情説明と協力依頼
いずれにしても、信頼性の高い証拠書類が求められるため、早めの準備が重要です。
障害認定日の誤認が招く不支給リスク
障害認定日を誤って解釈して申請すると、以下のような不利益が生じる可能性があります:
- 実際は該当する等級なのに、「申請日基準」で審査されてしまい不支給に
- 遡及請求ができたはずなのに、障害認定日が特定できず5年分(最大)の年金を受け取れない
このようなトラブルを防ぐには、制度に精通した専門家のサポートを受けることが有効です。
困った時は社会保険労務士に相談を
障害認定日やその前後の医療記録、診断書の収集は、制度に不慣れな方にとって非常にハードルの高い作業です。
社会保険労務士は以下のようなサポートを行います
- 認定日に関する医療記録の確認と整理
- 診断書作成に向けた医師との連携
- 遡及請求や事後重症の判断アドバイス
**一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください**
正確な知識と戦略で、あなたの申請をしっかりサポートします。
まとめ:障害認定日は申請成功のカギ
障害認定日は、障害年金申請の成否を大きく左右する基準日です。
診断日や申請日と混同せず、制度上の定義を理解し、的確な証明書類を準備することが大切です。
そして、難しいと感じたら早めに専門家に相談することが安心への第一歩となります。
プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
お知らせの関連記事
- 兵庫県立東はりま特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2026/01/23】
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 兵庫県立播磨特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2026/01/16】
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 主治医に「診断書を書いてもらえない」「申請を拒まれた」と感じている方へ
- 兵庫県立出石特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2025/11/07】
- 姫路しらさぎ特別支援学校様で障害年金勉強会を開催いたしました【2025/11/04】
- 【2025年最新】双極性障害で障害年金はもらえる?社労士が等級認定・金額・申請方法を徹底解説
- 診断名より“日常生活ができない”が大事!障害年金の本質に迫る
- 【2025年最新】うつ病の障害年金はいくらもらえる?社労士が申請条件から書類の書き方、コツまで徹底解説
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 夏季休業のご案内 2025年(令和7年)夏
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 兵庫県立播磨特別支援学校に通学されているお子様の保護者の皆様に向けてセミナーを開催いたしました
- 冬季休業のご案内 令和6年 年末年始
- 就労移行支援事業所ウェルビー姫路駅前センター様で障害年金学習会を開催しました!
- 明石市在住の方へ7月21日(日)無料出張相談会開催します!!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 冬季休業のご案内 2023年冬
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2022年4月)
- 【LINE・メールは受付可】年末年始休業のお知らせ
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2021年4月)
- コロナうつと思われる方へ障害年金請求のご案内
- 事務所移転の御案内
- 相談者から頂いたアンケート32(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート31(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート30(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート29(明石市)
- 相談者から頂いたアンケート27(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート26(加古川市)
- 相談者から頂いたアンケート25(朝来市)
- 相談者から頂いたアンケート24(揖保郡)
- 相談者から頂いたアンケート23(相生市)
- 相談者から頂いたアンケート22(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート21(加古川市)
- 相談者から頂いたアンケート20(鳥取県)
- 相談者から頂いたアンケート19(姫路市)
- 「年金生活者支援給付金」がはじまります。
- お盆期間の休業のお知らせ
- 相談者から頂いたアンケート18(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート17(高砂市)
- 相談者から頂いたアンケート16(姫路市)
- 相談者から頂いたアンケート14(加東市)
- 相談者から頂いたアンケート15(赤穂市)
- 相談者から頂いたアンケート13
- 相談者から頂いたアンケート12
- 相談者から頂いたアンケート11
- 相談者から頂いたアンケート10
- 相談者から頂いたアンケート9
- 相談者から頂いたアンケート8
- 相談者から頂いたアンケート7
- 相談者から頂いたアンケート6
- 相談者から頂いたアンケート5
- 相談者から頂いたアンケート4
- 相談者から頂いたアンケート3
- 相談者から頂いたアンケート2
- 相談者から頂いたアンケート1
よくあるご質問の関連記事
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 主治医に「診断書を書いてもらえない」「申請を拒まれた」と感じている方へ
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金をもらうために知っておきたいこと
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 冬季休業のご案内 令和6年 年末年始
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- 明石市在住の方へ7月21日(日)無料出張相談会開催します!!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 20歳前傷病の障害年金の対象者は? 受給ポイントや申請の注意点にについて社労士が解説!
- 冬季休業のご案内 2023年冬
- 緑内障でも受けられる!障害年金申請のための重要書類と手続き
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2021年4月)
- 年金生活者支援給付金でもらえる金額が改定されました
- 障害年金の種類ともらえる金額が改定されました
障害年金Q&Aの関連記事
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 主治医に「診断書を書いてもらえない」「申請を拒まれた」と感じている方へ
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- 年金額が変更?
- 障害年金を受給すると将来の老齢年金が減額する?法廷免除のままではリスクが高いので注意
- 保険料納付要件って?(4)
- 保険料納付要件って?(3)
- 保険料納付要件って?(2)
- 保険料納付要件って?(1)
- 業務上の事故で、労災保険法による障害年金を受けていますが。
- 障害年金がもらえる条件・病名は何?ほぼ全ての病気が対象?
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?【社労士が解説】
- 60歳まで国民年金に加入していましたが、今は加入していません。
- 現在の障害に新たな障害が発生した場合は、どうなりますか?
- 20歳前は国民年金に加入していないのに、請求できるのですか?
- 20歳前の障害基礎年金って、何ですか?
- 受診状況等証明書を作成するケースは?書いてくれないときの対処法も解説!
- 障害手当金について
- 初診日について
- 働いていても障害年金はもらえるの?
- 年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?
障害年金についての関連記事
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 診断名より“日常生活ができない”が大事!障害年金の本質に迫る
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金をもらうために知っておきたいこと
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 障害年金の不支給が増加!申請は社労士に依頼した方がいいのか
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 障害年金の『初診日』の考え方とは??
- 【親なきあと】3つの課題と解決策|『親が元気なうちにできること』を考える
- うつ病で引きこもり・寝たきりの方へ:障害年金申請をご検討ください
- 統合失調症で障害年金を受け取るには?認定基準や申請のポイントを徹底解説!
- 障害者手帳と障害年金、違いと関係性を知っていますか?
- ADHDで障害年金を受給できる?認定基準や申請のポイントを徹底解説
- 糖尿病で障害年金を受給するには?
- 障害年金の遡及請求とは?受給のポイントと注意点を詳しく解説
- うつ病など精神疾患は障害年金の対象です!申請・請求のポイントを徹底解説!
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- うつ病で障害年金受給にデメリットはあるのか?4つの注意点と申請手順を社労士が解説!
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- 人工関節(人工股関節)で障害年金はいくら貰える?申請/受給のポイント・必要書類を社労士が徹底解説!
- 【社労士が解説】障害年金をご自分で申請したい方へ【依頼した方が良い場合・違いがでる点】
- 傷病手当金が切れたら申請するべき障害年金とは?切れる前に申請するべき理由は?
- 【まとめ】脳脊髄液減少症で障害年金を申請したい方へ