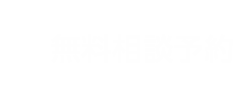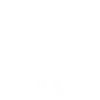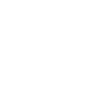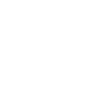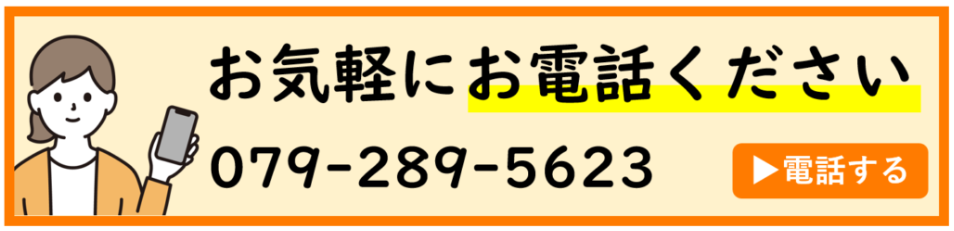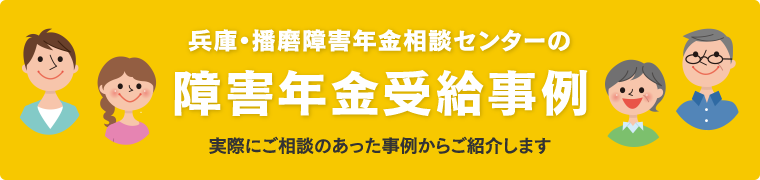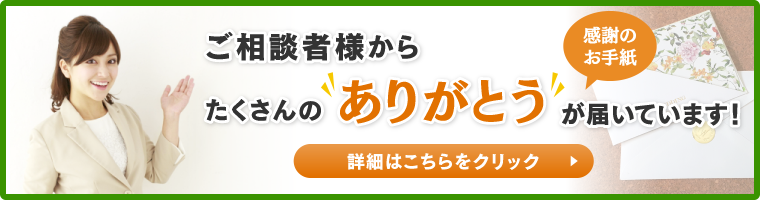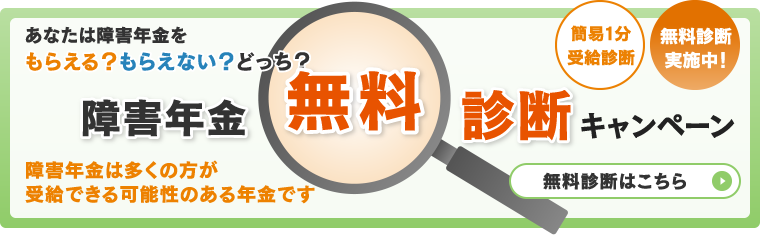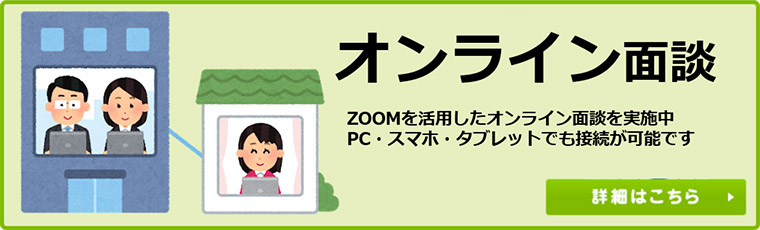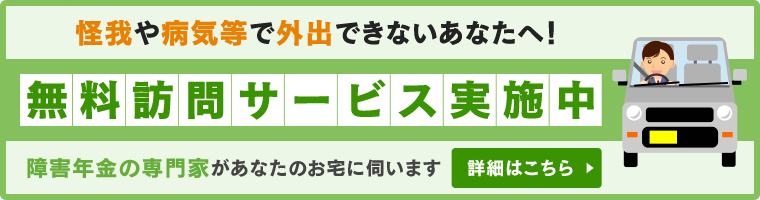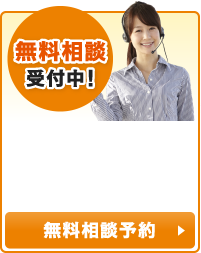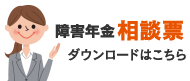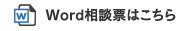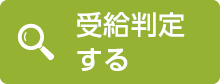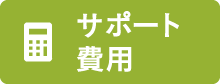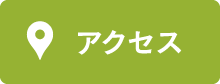脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金をもらうために知っておきたいこと
脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を受給するには、
症状の程度や日常生活への影響が審査のポイントになります。
申請の流れや等級基準、注意点をわかりやすく解説します。
目次
脳梗塞・脳出血とは?後遺症が生活に与える影響
脳梗塞や脳出血は、脳の血管に異常が生じることで起こる脳血管疾患です。
命に関わる重篤な状態となることもあり、
その後に麻痺・言語障害・視覚障害・認知機能障害・高次脳機能障害など、さまざまな後遺症が残る場合があります。
こうした後遺症が日常生活や就労に支障を及ぼしている場合、障害年金の対象になる可能性があります。
障害年金を受けるための基本条件
障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
・初診日が公的年金制度の被保険者期間中にあること
・障害認定日に一定の障害等級(1〜3級)に該当していること
・保険料の納付要件を満たしていること
脳梗塞や脳出血の初診日は、倒れて救急搬送された日や最初に異常を感じて受診した日となるのが一般的です。
後遺症による障害等級の目安
障害年金では、肢体の障害や言語障害、高次脳機能障害として等級が認定されます。
1級:ほとんど寝たきりで、日常生活すべてに介助が必要
2級:日常生活に著しい制限があり、外出や自立が難しい
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限があるが、生活はある程度自立して行える
たとえば、片麻痺で杖なしでは歩けない、階段昇降が困難、
言葉がうまく話せない、注意力が著しく低下しているなどの症状は、等級の対象となり得ます。
脳卒中後遺症の認定で重視されるポイント
日常生活での支障の程度(着替え、入浴、外出などが一人でできるか)
就労の可否や職場での配慮状況
身体機能だけでなく、記憶力や注意力など認知面も含めて判断
特に高次脳機能障害では、見た目では障害が分かりにくいため、
行動の逸脱や集中力の欠如、対人関係の困難さなどを具体的に医師に伝えることが大切です。
申請に必要な書類と流れ
障害年金の申請には以下のような書類が必要です。
📌障害年金裁定請求書
📌医師の診断書(肢体・言語・精神など該当する障害用)
📌病歴・就労状況等申立書
📌初診日の証明(受診状況等証明書)
📌住民票や戸籍謄本等の個人確認書類
書類の準備が整ったら、年金事務所または社会保険労務士を通じて提出します。
診断書の内容が最重要であり、医師には症状や支障を正確に伝えることが不可欠です。
社会保険労務士に相談するメリット
脳梗塞や脳出血の後遺症では、症状が複数にわたることが多く、認定にも専門的な判断が求められます。
社会保険労務士に依頼することで、
●医師への説明サポート
●認定に通りやすい資料作成
●申請の全体サポート
を受けられ、受給の可能性を大きく高めることができます。
まとめ
脳梗塞・脳出血の後遺症がある方は、障害年金の対象となる可能性があります。
症状が固定していれば(身体障害者手帳の交付など)ぜひ一度申請を検討してください。
手続きには複雑な部分もありますが、正しい準備と情報があれば、受給に近づくことができます。
「自分の状態で受けられるのか分からない」「書類の書き方が不安」という方は、
社会保険労務士に相談することで、安心して手続きを進められます。
プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は兵庫・姫路・播磨を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。
一人で悩みを抱えず、まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
よくあるご質問の関連記事
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 厚生年金から国民年金に変わると障害年金はどうなる? 就職・退職が多い若者の影響と注意点
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 主治医に「診断書を書いてもらえない」「申請を拒まれた」と感じている方へ
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 障害年金の「障害認定日」とは?誤解されやすいポイントを詳しく解説
- 冬季休業のご案内 令和6年 年末年始
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- 明石市在住の方へ7月21日(日)無料出張相談会開催します!!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 20歳前傷病の障害年金の対象者は? 受給ポイントや申請の注意点にについて社労士が解説!
- 冬季休業のご案内 2023年冬
- 緑内障でも受けられる!障害年金申請のための重要書類と手続き
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- ゴールデンウイーク期間中も個別無料面談を実施しております
- 障害年金受給額変更のお知らせ(2021年4月)
- 年金生活者支援給付金でもらえる金額が改定されました
- 障害年金の種類ともらえる金額が改定されました
障害年金についての関連記事
- 【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
- 受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
- 「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
- 診断名より“日常生活ができない”が大事!障害年金の本質に迫る
- 学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
- 障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
- 障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
- 障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
- 障害年金が不支給になった…審査請求・再審査請求で逆転できるのか?
- 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れる?働き方と等級の関係
- 障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
- 障害年金の不支給が増加!申請は社労士に依頼した方がいいのか
- 難病で障害年金は受給できる?対象となる病気や受給条件を詳しく解説
- 障害年金の「障害認定日」とは?誤解されやすいポイントを詳しく解説
- 障害年金の『初診日』の考え方とは??
- 【親なきあと】3つの課題と解決策|『親が元気なうちにできること』を考える
- うつ病で引きこもり・寝たきりの方へ:障害年金申請をご検討ください
- 統合失調症で障害年金を受け取るには?認定基準や申請のポイントを徹底解説!
- 障害者手帳と障害年金、違いと関係性を知っていますか?
- ADHDで障害年金を受給できる?認定基準や申請のポイントを徹底解説
- 糖尿病で障害年金を受給するには?
- 障害年金の遡及請求とは?受給のポイントと注意点を詳しく解説
- うつ病など精神疾患は障害年金の対象です!申請・請求のポイントを徹底解説!
- 障害年金は障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
- うつ病で障害年金受給にデメリットはあるのか?4つの注意点と申請手順を社労士が解説!
- 働きながら障害年金は受給できる?条件や申請ポイントを徹底解説!
- 人工関節(人工股関節)で障害年金はいくら貰える?申請/受給のポイント・必要書類を社労士が徹底解説!
- 【社労士が解説】障害年金をご自分で申請したい方へ【依頼した方が良い場合・違いがでる点】
- 傷病手当金が切れたら申請するべき障害年金とは?切れる前に申請するべき理由は?
- 【まとめ】脳脊髄液減少症で障害年金を申請したい方へ