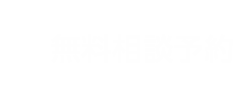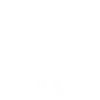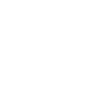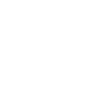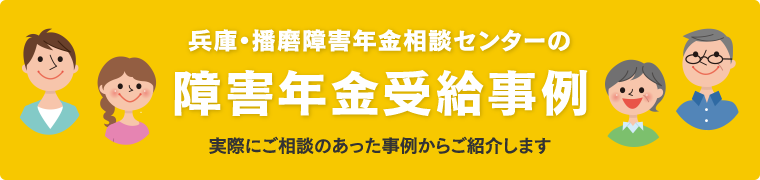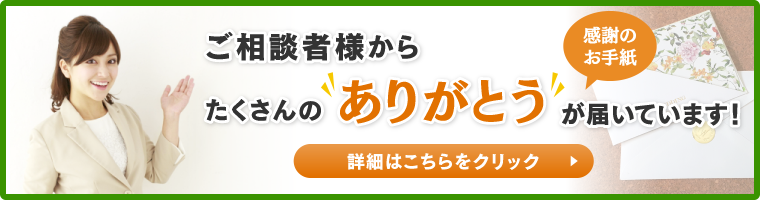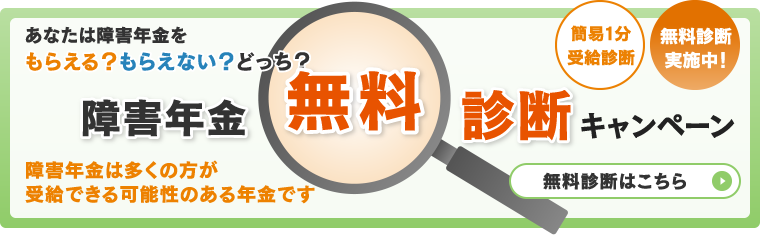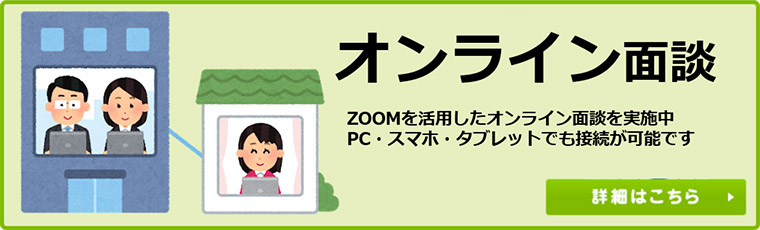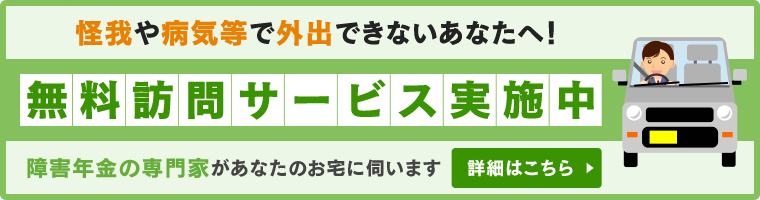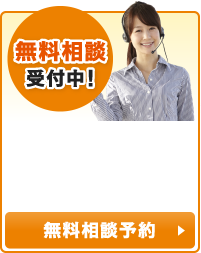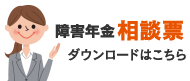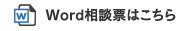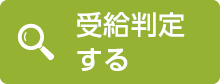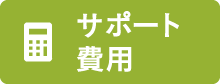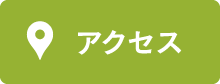障害年金について
【社労士監修】知的障害で障害年金はもらえる?等級の判定基準や療育手帳B2判定の可能性を解説
はじめに 「うちの子は知的障害がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?」 「療育手帳がB2(軽度)判定だと、年金は無理だと言われませんか?」 兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターには、このようなご相談が数多く寄せられます。 結論から申し上げますと、知的障害は障害年金の対象であり、適切な申請を行えば受給できる可能性は十分にあります。 ただし、単に障害があるという事実だけではなく、「日 続きを読む >>
障害年金3級はいくらもらえる?働きながら受給できる条件と計算方法を徹底解説
「病気やケガで仕事に制限があるけれど、完全に働けないわけではない。それでも障害年金はもらえるの?」 「障害年金3級は、1級や2級と何が違うの?」 このような疑問をお持ちの方へ。障害年金には、比較的症状が軽い場合や、働きながらでも受給の可能性がある「3級」という等級が存在します。しかし、3級は「厚生年金」加入者だけの特権であり、少し制度が複雑です。 本記事では、障害年金3級の受給条件、気になる 続きを読む >>
【社労士解説】発達障害 ADHD(注意欠如・多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?仕事をしていても受給できる基準と3つのポイント
はじめに 「仕事が長続きせず、転職を繰り返してしまう」 「大人になってから発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症)と診断された」 「周りと同じようにできない自分が辛い……」 発達障害は、見た目には分かりにくい障害であるため、職場や周囲の理解を得られず、経済的にも精神的にも追い詰められてしまう方が少なくありません。 兵庫・姫路・播磨障害年金相談センターでは、こうした発達障害に関するご相談が 続きを読む >>
受診状況等証明書とは?障害年金申請の「初診日」を証明する完全ガイド
障害年金の申請準備を進める中で、最初に立ちはだかる大きな壁が「初診日の証明」です。 「初診日」は、障害年金がもらえるかどうか、どの種類の年金(基礎または厚生)になるかを決定づける極めて重要な日付です。この初診日を公的に証明するための書類が「受診状況等証明書」です。 本記事では、障害年金申請の成否を分けるといっても過言ではない「受診状況等証明書」について、その役割から取得方法、病院でカルテが破棄さ 続きを読む >>
「もらえると思ってたのに…」障害年金と障害者手帳の“ズレ”にご注意!
「障害者手帳3級だから年金ももらえるはず」…実は、制度はまったく別物だった 「障害者手帳を持っている=障害年金を受けられる」は誤解です。 両制度の目的・認定基準は別。 手帳と年金が違う理由、実例、請求を検討するときのポイントをわかりやすく解説します。 はじめに―多くの人が勘違いする“手帳=年金”という思い込み 「障害者手帳が3級だから年金ももらえると思っていたのに、不支給になった…」 続きを読む >>
診断名より“日常生活ができない”が大事!障害年金の本質に迫る
症状名だけでは通らない。審査官が本当に見るものは「あなたの暮らしの困難さ」です 症状を持っているだけで年金が認められるわけではありません。 うつ病、発達障害、高次脳機能障害──どれも「診断名」を耳にすれば重く響く傷病ですが、それだけでは障害年金は支給されないことが多いのです。 審査で本当に問われるのは、「〇〇ができない」というあなたの 日常生活の制限。 朝起きられない、書類をまとめられない 続きを読む >>
学生のときに発症した病気でも障害年金はもらえる?
学生時代の発症は珍しくない うつ病や統合失調症、てんかん、難病などは、10代後半から20代前半にかけて 発症することも多くあります。 「まだ学生だったから年金なんて関係ない」と思いがちですが、 障害年金の制度は 学生のときに発症した病気やけが に対しても適用される場合があります。 結論から言えば、学生でも障害年金を受給できる可能性があります。 学生時代に発症した場合に関係する制度は? 続きを読む >>
障害年金とiDeCo・NISA:受給中でも活用できるの?
障害年金と資産形成の関係 障害年金は、生活の基盤を支える大切な収入ですが、 将来にわたって安心できる金額とは限りません。 そこで注目されるのが iDeCo(個人型確定拠出年金) や NISA(少額投資非課税制度) といった資産形成制度です。 「障害年金をもらっていると利用できないのでは?」と誤解されることもありますが、 実は両立は可能です。 iDeCoは利用できる? iDeCo 続きを読む >>
障害年金に子どもの加算がある??加算条件と金額を詳しく解説
障害年金に子どもの加算がある?? 障害年金には、子どもがいる場合に支給額が増える「子の加算」があります。 対象となる子の条件や金額、注意点をわかりやすく解説します。 障害年金の「子の加算」とは?基本のしくみを解説 障害年金には、一定の条件を満たす子どもがいる場合、年金額が増額される「子の加算」という制度があります。 これは扶養する家族の存在に応じて生活保障を手厚くする仕組みで、主に以下の 続きを読む >>
障害年金と労災保険の違いーどちらを優先して申請すべき?
仕事が原因で病気やケガをした場合 勤務中や通勤中の事故、あるいは仕事場でのパワーハラスメント等など、 精神的ストレスによる病気など「業務や通勤に起因するケガや病気」の場合には 労災保険 が適用されます。 一方で、仕事に関係なく日常生活の中で発症した病気やケガで障害が残ったときには 障害年金 が支給されます。 同じ「障害」であっても、原因や状況によって受けられる制度は異なるため、 最初にど 続きを読む >>